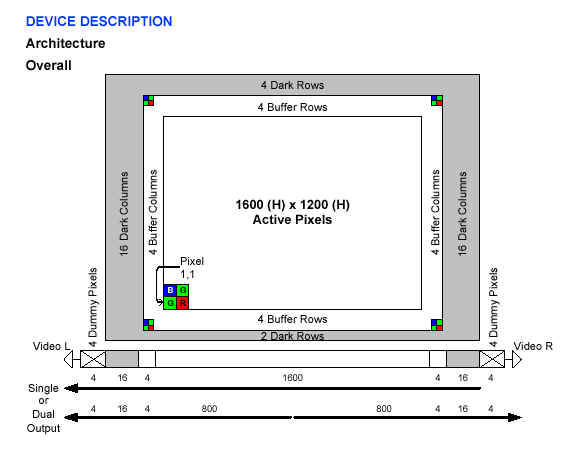BJ−40Cと他機種との比較 2004.11.03

BJ−40CとSBIGのスペック比較です。
チップサイズ等はSBIG ST−7XMEと同等ですが・・

|
製品仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
SBIGのスペック
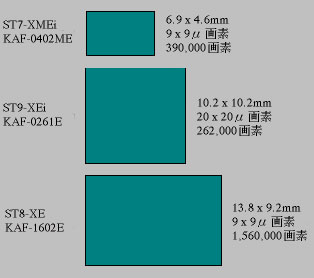
BJ−40Cと比較するのは酷ですが、
|
|
|||||
| カメラ機種名 |
|
|
|
|
|
| 搭載CCDチップ |
|
|
|
|
|
| 合計画素数 |
|
|
|
|
|
| アレーサイズ |
|
|
|
|
|
| チップ面積 |
|
|
|
|
|
| 画素面積 |
|
|
|
|
|
| チップタイプ |
|
|
|
|
|
| 標準チップクラス |
|
|
|
|
|
| 販売価格 |
|
|
|
|
|
| チップオプション |
|
|
|
仕様あり |
|
|
|
|
| CCDチップ | 米国TI社 TC237(656 X480/314,880 画素、6.9 X4.6mm 7.4X7.4μm) |
| 冷 却 | 一段空冷ペルチェ装置(自動温度設定) |
| シャッター | 回転式機械式シャッター内蔵 |
| 減光フィルター | 減光フィルター内蔵 |
| 映像出力方式 | 5"LCDモニター/アナログビデオ出力/RS232(パソコン) |
| 露光時間 | 1/100 秒〜600 秒まで設定可 |
| 感 度 | 口径20cm 使用で1 秒の露光で約14 等級(60 秒で約18等級) |
|
|
|